ことし9月に横浜市駐車場条例の改正素案が公表されました。新聞報道によると横浜市都市整備局は2026年7月の改正条例適用を目指しているようです。この条例は、私が新聞記者として取材しているころから、賛成や反対を含めて色々な話を聞いていたので、改めて改正素案をじっくりと読んでみて、まちづくりや建設業界への影響は大きいだろうと感じました。
その1つは、近い将来、日本国内において自動運転自動車が登場(すでに米国ではたくさん登場していますけど)することで、駐車場の確保よりも車寄せの必要性が高まると考えていたからです。将来的に自動運転自動車が世の中に広まって、移動手段の主流となると、鉄道の駅前に設けられた駐車場は、広大な「都市の空き地」としての価値が生じる可能性があります。
もう1つは、「既存不適格の問題」です。これまで駐車場整備地区等において1,000㎡以上に義務付けられていた駐車場の附置義務が、2000㎡以上に引き上げられます。1,000㎡以上2,000㎡未満の既存建築物は、駐車場附置義務から除外されたので、駐車場を置く義務がなくなります。駐車場が収益を上げていれば問題はないのですが、収益を上げられていなかった場合、建築物のオーナは不良資産である駐車場を廃止してしまうことが考えられます。
しかし、これは「既存の駐車場を無条件に他の用途へ変更してよい」という意味には直結しません。理由は、建築基準法に定められた「容積率」の規定にあります。建築基準法では、建物の延べ面積のうち、駐車場の用途に供する部分の面積は、全体の延べ面積の5分の1を上限として、容積率を計算する際の延べ面積から除外できると定められています。多くのデベロッパーや建築主は、この緩和規定を最大限に活用し、定められた容積率の上限ギリギリまで事務所や店舗、住居などの収益部分の床面積を確保して建物を建設しています。
店舗や事務所など容積率の計算対象となる用途へ変更する場合、その面積が建物の延べ面積に加算されることになります。その結果、建物全体の延べ面積が、都市計画で定められた指定容積率を超過してしまう可能性が非常に高くなります。建設当初から容積率に十分な余裕を持って設計・建築された建物であれば、その余裕の範囲内で駐車場の用途変更が可能です。しかし、経済合理性を考えると、そのような建物は稀であると推測されます。
2,000㎡未満の小さなビルは、建物の1階部分に駐車場を設けるケースが多いと思います。路面に面しているため、店舗やオフィスに転用できれば、収益の大幅な改善が見込めます。経済的には転用したいが、法的には転用できないというジレンマが状況が生じることになります。建築主が行政への届出を行わずに、無許可で駐車場を内装改修し、他用途(倉庫、店舗、事務所など)に転用してしまうケースが発生する可能性があるでしょう。
建物の1階部分は、まちの「賑わい」に取って重要な要素です。横浜市は「横浜都心機能誘導地区建築条例」で、都心部に共同住宅を建てる場合、周辺市街地環境にふさわしい商業・業務系の用途の導入を行うことを求めています。駐車場の入り口も道路に面した1階部分にあり、ここが変わることは、まちの「賑わい」に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。
新築の小さな(2,000㎡未満)の建物は、これまでよりも地域の「賑わい」に貢献できることになりますし、既存建築物においても、既存不適格の問題を解消できる手段があれば、周辺地域とビルのオーナともに、大きな効果を生み出せるのではないでしょうか?今回の公表は改正素案でしたが、最終的にどんな改正が行われるのか期待して見守りたいと思います。
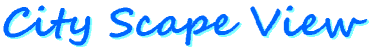


コメント