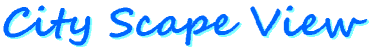建築物/構造物 画像集
建築物/構造物 画像集 根岸森林公園トイレ「丘の小道」
横浜市の公共建築100周年記念事業の一つとして開催された「根岸森林公園トイレ設計コンペ」で最優秀賞を受賞したのが「丘の小道」です。受賞者は甘粕敦彦と張昊の2人がつくった提案で、12月8日には小中学生が参加した植栽ワークショップが開かれ、実際に建築物を見られると言うことでしたので取材しました。土壁のような壁は本当に現地の土を使っているようで、柱などの木材、鋼板の屋根工事を含め、上手く周囲の風景に融け込ませていました。子どもたちの植えた草花が大きくなれば一層、異物感を薄めることができると思います。建物はまもなく竣工を迎え、12月21日(土曜日)から使えるようになります。これに先立ち、17日(火曜日)午後3時から完成披露会と見学会が開かれます。